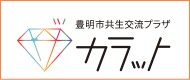生活情報RECRUIT
子どもの熱中症
元気のないときは注意?熱中症の症状とは
子どもの熱中症は、保護者や大人が周りにいるため、早期の段階で発見されるので重症化することは多くはありません。ですが、万が一、熱中症が重症化してしまうと生命に危険がおよぶ可能性も出てくるので注意が必要です。熱中症の代表的なサインは次の通りです。
- 頭痛を訴える
- 嘔吐した、吐き気を訴える
- 熱が出ている・寒気を訴える
- いつもより元気がない、しんどそうにしている
- ふらふらしている・目がまわる(めまい)という・からだの痛みを訴える
- 鼻血
- 手足のしびれ
また腹痛や下痢の症状が出ることもあります。
さらに重度の熱中症の場合は、下記のように誰がみても明らかな異常を示します。
- 意識がない
- からだが痙攣(けいれん)している
子どもは体調の異変を言葉にできないことを理解する
特に炎天下で遊んだときなどは周囲が子どもの様子に変化がないかを確認し、異常があればなるべく早期に対処することを心がけましょう。熱中症は対策が何より大切です。しかし、いくら対策をしても熱中症にかかるときはかかってしまいます。万が一、熱中症になってしまった場合、保護者の方・大人がなるべく早期に気づいてあげることが重要なのです。
子どもの場合、「気持ち悪い」「お腹が痛い」は熱中症のサインかもしれない
子どもはボキャブラリーが不足しているので、体調が悪いことや、のどが渇いたなどということを的確に訴えることができません。たとえば「吐き気がする」ときに「お腹が痛い」と訴えたりします。保護者の方は子どもをよくみておくことが重要になります。
熱中症の重症分類
熱中症の重症分類はわかりやすいように下記の3つにわけて考えることがあります。
熱中症のⅠ度
めまい、大量の発汗、失神、筋肉痛、こむら返り(ふくらはぎの筋痙攣、一般的には足がつるといわれる)
熱中症のⅡ
頭痛、嘔吐、倦怠感(けんたいかん:からだがだるい)など
熱中症のⅢ度
意識がない、痙攣など
しかし、この分類はあくまでもわかりやすく理解するための分類で、明確に3つに分かれるわけではありません。つまり、この分類にこだわる必要はないのです。
熱中症の初期症状
熱中症の初期症状としては次のものがあります。
頭痛
子どもが頭痛になると、「頭が痛い」や「ガンガンする」「ズキズキする」「ドクドクしている」などと訴えケースが多いです。まだ幼く、自分の症状をうまく伝えられない子どもの場合、泣き出してしまうこともあります
嘔吐
子どもに吐き気があると、「気持ち悪い」「おなかが痛い」と訴えるケースが多いです。また、実際に吐いてしまうこともあります。
発熱・汗をかく
体に熱がこもると、体がほてったり、発熱や体温が高くなったりすることがあります。また、大量に汗をかくことがあります。
子どもの元気がない
熱中症にかかると倦怠感が生じるので、子どもも普段と比べると元気がなくなり、しんどそうにします。また、ぐったりとすることもあります。
その他、
- めまい
- からだが痛む
- 目の焦点があっていない
などの症状が現れることがあります。
重度の熱中症の症状
「意識がない」「体がけいれんしている」といった場合はすぐに医療機関へ!
重度の熱中症の場合、「意識がない」「からだが痙攣している」と一目みておかしいとわかります。こうした症状が見られた場合、急いで医療機関へ行くことをおすすめします。
熱中症が重症化するのはどんなとき?
重症化すると怖い熱中症ですが、実は子どもの熱中症で重症化するケースはほとんどありません。記事1でご説明したとおり、子どもは体質上、熱中症になりやすく、高温の環境にいるときには重症化もしやすいといわれていますが、保護者や大人が子どもを見守っているので早期の段階で発見されることが多く、重症化することが少ないのです。
しかし、子どもは運動に集中していると水分補給を適切にできないことがあり、その結果、重度の熱中症になってしまうケースもあります。そうならないためにも、保護者の方・大人の注意が必要といえるでしょう。
重症化する可能性があるのはどんな子ども?
- スポーツに熱中している子ども(特に炎天下のなかで運動に集中している場合、水分補給を忘れがち)
- 炎天下、乳幼児を車内に長時間置き去りにする
など、特別なケースです。こういうケースでは、重症化しやすく命の危険もあります。
熱中症にかかるのは夏だけでない
熱中症は熱を体内に溜め込んでしまうことが原因なので、夏に多くみられます。しかし、夏にしか熱中症にかからないわけではありません。
たとえば季節外れにもかかわらず、急に暑くなった場合です。この場合、からだが急な暑さに慣れず、熱中症になってしまうのです。これには、子どもが熱中症になりやすい理由の一つである、暑さにからだが順応することに時間がかかることと関係している部分もあります。
子どもの熱中症は重症化が少ないのはなぜ?
子どもの重症熱中症の頻度はとても少ないです。
というのも、子どもは常に保護者や周りの大人たちに見守られており、熱中症の症状が早期の段階で見つかり、治療できるからです。むしろ、熱中症で重症化する可能性は独居の高齢者のほうが高いといわれています。
子どもの熱中症については、過度な重症化の心配は必要ないと言えるでしょう。また、子どもの熱中症は自宅でも治療し、治癒することが可能です。
子どもの熱中症、自宅でできる対処法について
重症のケースを除けば、家庭での適切な対処で熱中症の症状は改善します。熱中症の場合、
・からだを冷やす
・ゆっくり休ませる
・水分補給をする
以上が主な対処法になります。軽度の熱中症の場合、これらを行うだけで、症状はずいぶん改善するはずです。
からだを冷やす
涼しい場所に避難し、熱くなったからだを冷やすようにしましょう。できればクーラーの効いた部屋などが望ましいです。また、水で絞ったタオルを首の両脇、脇の下、大腿の付け根に当てるなども効果があります。
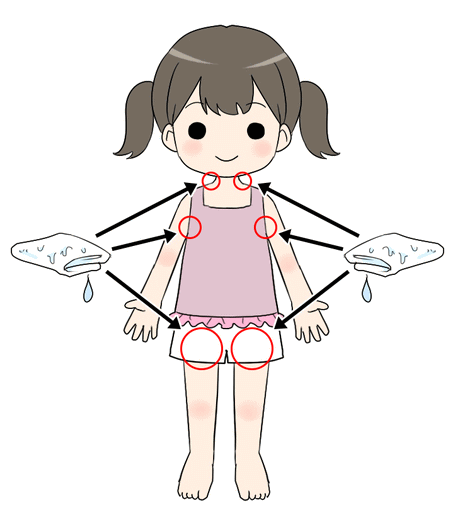
ゆっくり休ませる
衣服を脱がし、子どもが楽な体勢でゆっくり休ませましょう。
水分補給をさせる
スポーツドリンクや経口補水液に絶対的にこだわる必要はなく、基本、子どもが飲みたいといったものを飲ませて構いません。重要な点は水分を補給させることです。少し薄めたリンゴジュースが飲めるようであれば、それを飲ませるのもよいといわれています。
熱中症のときに解熱剤は使わない
熱を下げようと解熱剤を使用しても、熱中症の場合、熱は下がりません。涼しい場所で、体を冷やし、ゆっくり休ませることで自然と熱は引いていきます。
子どもが頭痛を訴えている場合には、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱鎮痛剤(発熱がみられる際に処方されている薬)を使用すれば頭痛の症状を緩和することができます。
子どもが熱中症になったときの食事
子どもが熱中症になった場合や汗をよくかいた日は、ミネラルと塩分の補給が大切です。ミネラルや塩分が補えるメニューにするとよいでしょう。
ミネラルのある麦茶
麦茶にはカリウムなどミネラルが含まれています。麦茶なら子どもも飲みやすく、食事の際など、麦茶を普段より多めに飲むようにするとよいでしょう。
塩分とミネラルが補給できるみそ汁
味噌には塩分とミネラルが多く含まれています。子どもが熱中症にかかった場合や汗をよくかいた日は、食事にみそ汁を添えてあげるとよいでしょう。
症状が回復したら
症状がよくなったら普通の食事に切り替えても問題ありません。念のため、意識して麦茶やみそ汁をだすのもよいでしょう。
熱中症の病院での治療について
症状が軽度であれば、病院を受診しても、先ほど解説した家庭で行える対処と変わりはありません。自力で水分補給できないケースには、点滴をして水分補給をすることがあります。
重症の熱中症の場合には医療機関での集中治療が必要
重症の熱中症の場合、集中治療が必要になります。重症化してしまうと、臓器不全が起きることもあります。腎不全や肝不全の症状がみられた場合、気管挿管(きかんそうかん:鼻または口から気管チューブを挿入し気道を確保する方法)・人工呼吸器管理(じんこうこきゅうきかんり:人工呼吸器による呼吸管理)、点滴治療、血液透析など症状にあわせた対症療法で臓器不全の治療を行います。
FAQ:「子どもが熱中症になったらどのような対処をすればいいでしょうか。また、どういう場合、医療機関にいくべきですか?」
対処法
・涼しい場所に移動
・ゆっくり休憩
・水分補給
子どもが飲めるものを飲ませて、スポーツドリンクや経口補水液にこだわらなくてもよいです。
医療機関にいくべき状態
・意識がない、痙攣しているなど、一目で様子がおかしいと判断できるような場合には重症である可能性があります。救急車を呼ぶなりして、急いで近くの医療機関に行くようにしましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
愛知県ではヘルプマークの配布が2018年7月20日(金)より始まりました。
愛知県では、平成27年12月制定の「愛知県障害者差別解消推進条例」に基づき、障害のある方が生活を送る上でのハード・ソフト面でのバリアフリー化に向けた環境整備を進めています。
この度、その取組の一環として、「ヘルプマーク」について、平成30年7月20日(金曜日)から、県内一斉に配布を開始することとしました。
ヘルプマークの普及にあたっては、県民の皆様お一人お一人の御理解と御協力が必要不可欠です。
県民の皆様におかれましては、電車・バスの中でヘルプマークの利用者を見かけましたら席をお譲りいただいたり、困っているようであれば進んでお声がけいただくなど、「思いやりのある行動」をお願いします。
「ヘルプマークとは」
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が平成24年10月に作成したマークです。
ヘルプマークには、ストラップが付いており、鞄などに付けることができます。また、附属物として、シールが付いているので、必要な支援をシールに記載し、マークの裏面に貼付することができます。
「配布方法について」
①配布開始日
平成30年7月20日(金曜日)
②主な配布場所
・各市町村障害福祉担当
・県保健所
③配布条件
・御希望の方に無償で配布します。援助や配慮を必要とする方であれば、どなたでも御利用いただけます。
・上記の窓口で、職員からマークの趣旨を説明の上、お一人につき1個配布します。
・口頭での申出で可とし、障害者手帳、身分証明書の提示や申請書等の提出は不要です。
・御家族や支援者等の代理人による受取も可能です。その際にも、障害者手帳の提示等は不要です。